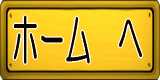

「ミニ観葉」
ひと昔前、「ミニ観葉」という、小さな植木がはやったことがあった。 手のひらにのるような本当に小さなもので、鉢をいれても十センチほどの高さだろうか。三ミリほどの幹に数本の枝をつけ、葉は小指の爪の半分ほどで、まだ薄緑色で幼い。試しに私も買って、勤務先の私の机に置いてみることにした。 元来、草木には興味のない性質であったが、出勤すると一番に植木に水をやるようになり、愛着をもつようになった。 私の机は窓に近く(「窓際族」ではなかったが……)、ブラインド越しに日ざしが入ることもあって枯れずにいた。 数人の女子社員達も、当初は珍しさもあって、「かわいいッ!」を連発していたが、やがて見向きもしなくなった。が、一人の女子社員だけは、私が不在のときに、植木に水をやってくれているようだった。 デスクワークの合間に手にとってみたり、電話の合間にフーッと見つめたりして、私にとって「ミニ観葉」は、ある種の存在感を持つようになった。 本格的な梅雨に入り雨脚も激しく私の病もいよいよ険しさを増して、明日再入院ということになり、机とロッカーを整理した。 おそらく復職することはできないだろうという思いだったが、特に感傷的な気持ちにはならず事務的に処理した。 これから先のことは、まだ漠然として把握しかねていた。切迫した状況になるまで曖昧にしておこうという気持ちもあった。 デスクマットや椅子のクッションまで処分したところで、「ミニ観葉」だけがポツンと残った。 幹は幾らか太くなり、葉は緑を濃くして、全体に一回り大きくなっただろうか。当初よりはたくましくなったような気がする。 (さて、どうしたものか) と、窓外の雨を見つめながらも妙案は浮かんでこない。駐車場の片隅にでもと思うが、いかにもミスマッチで気乗りがしない。 激しい雨脚に気を取られ集中しかねていた。 長い間、立っていると腰から崩れ落ちそうになる。病は容赦なく進行している。 「あのうー、その植木、私にお預かりさせていただけませんか?」 「えっ!」 私は、予想外の展開に言葉が出なかった。 私が不在の時、植木に水をやってくれている女性である。 「大事に育てますから」 「そう、そうしてくれると助かるね」 私と彼女の視線が「ミニ観葉」に集まった。彼女は腰をかがめ、視線を植木の高さに合わせ、 「大きくなりましたね」 と言って前髪を払った。 彼女は入社二年目である。面長の顔立ちで、派手な目鼻立ちではないが、バランスがよく、笑うと八重歯をのぞかせる。 「ちょっと、よろしいですか?」 彼女は植木を手に取ると高くかざした。 あごのラインがとてもきれいで、小さなホクロがある。 地味で印象がうすいためか、まだ、男性社員には注目されていないようである。 「あのー、この植木、名前はなんていうんでしょうか?」 二十歳近く年下の女性に好意をもつのは、照れ臭く厄介なことだが悪い気はしなかった。 「あのー……」 「うん?なに?」 「名前です、植木の」 彼女は苦笑しながら八重歯をのぞかせた。私がうわの空だったことを笑ったのだろうか。 その時、唐突に、知的で素朴な女性は美しい、と思った。 「名前ねえ……」 植木を買ったときは、名前が書いてあるタグが鉢に挿してあったが、いつのまにか紛失してしまった。 「忘れた!」 「……」 たしか、カタカナの長い名前だったようだが、思い出せない。 彼女は、明らかに不満の表情をした。彼女は彼女なりに、植木に愛着をもっているようだった。 「あの植木の名前ね、ショウコにしたらどう?」 「……」 「ショウコ」とは彼女の名前である。 冗談のつもりだったが、まんざら悪くもないな、と思った。むしろ、いいアイデアでは、と一人悦に入っていた私とは裏腹に、彼女は納得しかねる表情で植木を見つめていた。冗談をそしゃくしえない清潔さを感じさせた。 彼女は、上司に呼ばれ、不満げな表情を残したまま立ち去った。 この頃、私は杖を使っていた。当初は持て余し気味だったが、今は欠かせない必要品になった。持っていないと足元がおぼつかない。 杖を使うことになんのためらいもなかった。世間体など気にする無駄な労力などとれなかった。楽になれば何でもよかったのである。 ハンディキャップが、私に居直ることの心地好さを教えてくれた。 そろそろ昼休みである。彼女が戻ってきたら退社するつもりである。 引継ぎの事務手続きは終わっていたし、私の後任人事は内定しているはずだが、辞令はまだでていない。 私の入院が長期になる、と報告した段階ですぐ人事は動きだしたようだった、やむを得ないことではあるが……。 私の欠勤は、有給休暇で処理された後人事部付けになり、白旗をあげることになる。 彼女が戻ってきて、私の机の左側に立ち止まった。 なにがあったのか、彼女はニコニコ嬉しそうに植木を手に取ると、 「あのー、この植木の名前決めました!」 と、八重歯をのぞかせた。 「アキラにします」 「えっ!」 今度は、彼女が私に冗談を言ったのだろうか。私は、彼女の晴れやかな表情を見ながら、どういうことなのかと困惑した。 雨が、また激しく窓をたたいた。 あれから十年近く経って、私の病はほとんど究極まで進行するに至った。手足は動かず、人工呼吸器をつけ、寝たきりの生活を甘受している。 まさか、まさか、と思いながらもその都度私の祈りは裏切られ続けてきた。さまざまな試みや意志は、ことごとく徒労に終わったかのように思える。いまや、その残骸に言葉もない。 通り過ぎてきた苦難に思いをはせれば涙は熱い。悲しみの涙でも、悔し涙でも、無念の涙……でもない。ただただ、自らの鎮魂の涙である。 足が……、手が……、呼吸が……。 気管切開直前前の狂おしいまでの逡巡は、死に直面した長い時間でもあった。 とまれ、よく乗り切った、と思う。乗り切る力などなかったはずだが、生きていれば乗り切れるものだ。 が、しかし、死を必ずしも否定するものでもないし、その立場にもない。私には(私に限ったことでないのかもしれないが)、死が選択肢の一つだった時期があったからである。 ALSといういまだ治療法の確立されていないこの病に、もちろん希望を捨ててはいないが、あからさまにもってもいない。この微妙なスタンスがALSに対する私の意地でもあろうか。 気管切開からおよそ五年。その分、神に依存する都度が少ない、と言えるであろうか。 人工呼吸器を装着しているため、事故はいつでも起こりうる。死が日常的に、さりげなくスタンバイしている状況である。 日々の生活の中で、なんの脈絡もなく唐突に思い出すのがあの「ミニ観葉」のことである。枯れずにいればどのくらい生育しただろうか。小さな白い花でも咲かせただろうか。あるいは、枯れてしまったかもしれない……などと。 それにもまして思い出すのは、植木を預けた彼女のことである。 今は結婚して育児に忙しい日々を送っているのだろうか。それとも、まだ現役で働いているのだろうか。 思い起こせば豊かな想像は私の意志が追いつかぬほどに駆け巡る。懐かしいのかきりがない。その間隙をぬって、曖昧で微妙ながらも彼女の笑顔が浮かんだ。 妄想たくましいのは、寝たきりの病人にとって得意の分野である。 どさくさにまぎれて、どうでもいい人(失礼)の面影まで浮かぶ。こちらは、どういう訳か鮮明に浮かぶ。 はがゆいおもいをしながらも、私は、彼女の面影が消えないように、そっと、また眼をとじた。と同時に、忘れていたあの「ミニ観葉」の名前が、刺激的に必要以上に鮮明に蘇ったのである。 閉塞していた脳細胞の一部に血流がとおり、さわやかな風が吹き抜けたような、清清しさを感じた。思い出せなかったことが突如蘇った時の、あの快感である。 「ミニ スイート キャロット」 ミニスイートキャロットである。 私は、その快感を楽しむかのように、忘れていた植木の名前を慈しんだ。 ミニスイートキャロット、ミニスイートキャロット、ミニスイートキャロット……と。 私は、しばらくその快感を楽しんだ後、強力な接着剤で記憶の片隅にその植木の名前を張り付ける作業をした。 ミ・ニ・ス・イー・ト・キャ・ロッ・ト そうしなけらばおさまらない、なにかしらの焦燥感を抱いていたからである。 しかしながら、最早そんなことは忘れてもいいことではあるのだが……。 私は顔を歪め、口をひきつらせながら微笑んでいた。 ……でも、なんで微笑んだのか、私にもよく分からなかった。 (注)このエッセーは、病状が進行してからは額にとりつけたセンサーでパソコンを操作し「書いた」ものです。 指のようにはいきませんが、意思伝達には十分その機能を果たしてくれます。極めて軽量で、着脱や操作は簡単です。 日本ALS協会本部の野田さんに御尽力頂き、千葉支部の高橋さんに取りつけて頂きました。ありがとうございました。 |